鴎外研究に不可欠な「作品」である『椋鳥通信』に着目する
森鴎外の西洋百科事典 『椋鳥通信』研究
金子幸代著/森鴎外は雑誌「スバル」で1909年(明治42)から1913年(大正2)にかけて『椋鳥通信』を計55回連載し、その内容は多様で幅広い欧米各地の情報を伝えている。情報源となったドイツの新聞「ベルリナー・ターゲブラット」の記事を、梗概・翻訳の名人である鴎外が自分の見解をうまく盛り込み読者に欧米の最新情報を提供した。本書はその『椋鳥通信』に関連する論文5篇と、巻末に「ベルリナー・ターゲブラット」に関する資料を付す。
A5判上製カバー装・244頁/定価(本体4,500円+税)
ISBN978‒4‒903251‒15‒8
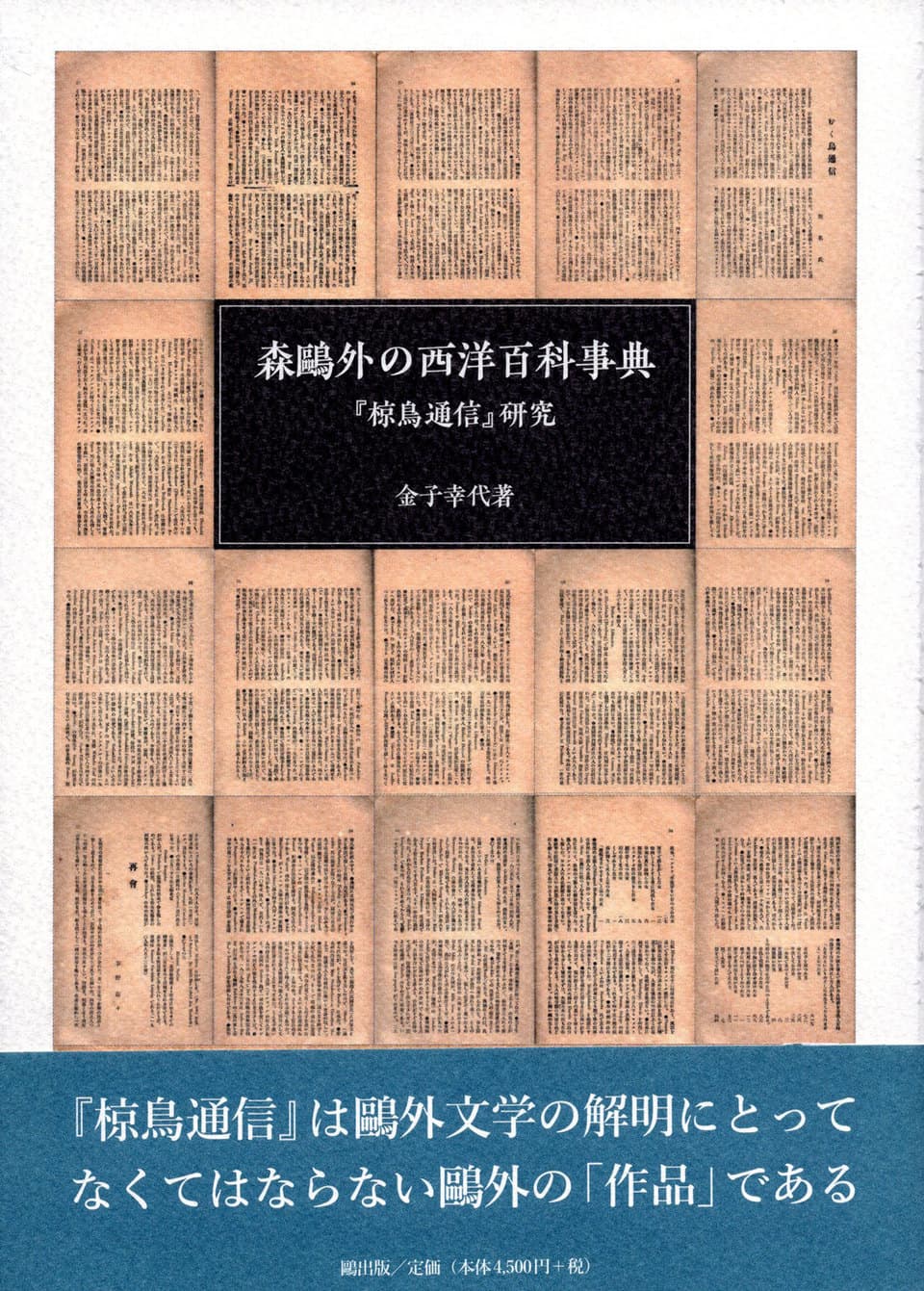
鴎外の『椋鳥通信』は、鴎外研究史においてこれまで研究の対象とみなされたことがほとんどなかったと言えるだろう。今回、「『椋鳥通信』研究」と題した著書を出版するにあたって、そのように先行研究の乏しい研究状況のなかで、どのような意図で出版しようと考えたのか、ということを説明しておく必要があると思う。
鴎外の西洋文化紹介と呼べる『椋鳥通信』について、なぜこれまで真正面からの研究がなされてこなかったのか、という理由は三つあると思う。第一の理由は分量の問題である。『鴎外全集』で九〇〇ページにも及ぶ圧倒的な量である。ひと通り読み通すだけでも大変な時間と労力が必要である。第二の理由はその内容である。演劇、小説、美術など芸術関係の他、政治、事件、犯罪、科学など雑多な内容が無秩序に紹介されていて、とりとめのない印象がある。さらに、人名や作品名などが原語で書かれているので、はなはだ読みにくい。取り上げられている作家も、トルストイやストリンドベリなど大物もいるものの、今日では忘れられた作家や芸術家も多く、興味を引かない。第三の理由は、これが研究の対象と認められない最大の理由であろうが、『椋鳥通信』には種本ならぬ、種新聞があることである。種新聞の「ベルリナー・ターゲブラット」と『椋鳥通信』の関係については本書の資料編において証明しているが、いずれにせよ鴎外の創作ではなく、当時のドイツの新聞の文化欄から興味を覚えた記事を抜粋して紹介しただけであり、オリジナリティがない、したがって、鴎外研究の対象にはなりえない。以上のように考えられてきたのである。
しかし、私は『椋鳥通信』は鴎外研究において欠くことのできない対象であると以前から考えていた。その理由も三つある。ひとつ目は、種新聞があったといっても、当然ながらその文芸欄の記事すべてを引用するわけにはいかない。取捨選択という作業が必要になる。そして取捨選択においてはおのずから鴎外の鑑識眼が発揮されるのである。その鑑識眼には、「神は細部に宿る」で、鴎外という作家の本質が潜んでいる。この問題に関連して、翻訳という問題もある。梗概の名人技で知られる鴎外だけに記事の要約はお手のものであったし、その前提となる翻訳の腕もゲーテ『ファウスト』の名訳に見られるように、折り紙つきのものであった。種新聞があっても、その記事は翻訳の巧拙によって生きたり、死んだりする。二つ目の理由は、『椋鳥通信』は「通信」と銘打っているだけに、その宛先人がいる。それは、もちろん「スバル」の読者である。しかも、原語がふんだんに盛られているように、読者のなかでも独仏語を少なくとも発音でき、西洋文化について基本的な知識のあるインテリ層である。それら限定された知的読者層を想定しているだけに、鴎外は自らのもっとも伝えたいことを紹介しているとも言えよう。種新聞があっても、その記事を紹介するなかで、自らのもっとも伝えたいこと、すなわち自分の見解をうまく盛り込んでいる、と考えられる。種新聞があるだけに、逆に自分の意見を公然と伝えることができた、と考えられるのである。三つ目の理由は、読者に西洋の情報を定期的に伝える、という単純作業のなかで、鴎外も同時代の西洋の社会、文化、政治といったものの全体像がつかめるようになったことである。なにしろ、ドイツ留学を終えてからすでに二五年近く経過しているのだから、このような西洋紹介の機会がなければ、鴎外にとって同時代の西洋の全体像の把握はむずかしかったであろう。そして、そのような同時代の西洋の全体像の把握は、当然ながら鴎外の創作にも種々の影響を与える。『椋鳥通信』の執筆は、鴎外の創作にとっても種々の刺激を与えることになったのである。
以上の三点で明らかになったように、『椋鳥通信』は鴎外文学の解明にとって、なくてはならない研究分野である。「西洋百科事典」という題名をつけたのも、読者に提示するために鴎外が編集した「西洋百科事典」であるという意味と、鴎外が同時代の西洋を理解し、自らの創作の刺激にするための自家用「百科事典」というふたつの意味を持っているからである。このふたつの意味の解明だけでも、『椋鳥通信』研究は充分な意義があると言えるだろう。(本書「はじめに」より)
